2025年7月17日更新しました
読書感想文は「本選び」から始まります。
ここで自分の興味のある本を選べるかが重要なのです。
読書感想文を上手く、スムーズに書くための本選びのお手伝いとして、中学・高校受験で出題された本を中心に、読書感想文が書きやすい本をテーマ別に選んでみました。
- なんでテーマ別になっているの?
本が書かれているテーマが読む前からわかっていると、読んでいるうちからどんな感想文を書こうかと考えやすくなります。
- どうして中学・高校受験で出題された本を選んでいるの?
受験で出題された本は、国語のエキスパートである先生が「読んでほしい」おすすめ本のはずだからです。
お気に入りの読書感想文用の本を選んで、読んで、自分の考えや気持ちを原稿用紙にぶつけてみてください。
せっかく本を読むなら、入試に出た本を読んでみませんか?
このブログでは、中学入試・高校入試で出題された本のなかから選んでいます。なぜなら……。

入試で出題されたというと、堅苦しいと思うかもしれませんが……。
中学・高校受験出題本はとにかくおもしろい!
国語の専門家である国語の先生たちが選んだ本はどれも失敗なし!なのです。
感想文の書き方
読書感想文を書くための本を読む前に、読書感想文の書き方やコツを知っておくのがおすすめです。
『カンタン! 齋藤孝の 最高の読書感想文』

感想文を書き始める前に読んでみて
●画像をクリックするとアマゾンへ
【著者】齋藤孝
【出版社】KADOKAWA(角川つばさ文庫)
小説ではありません
●あらすじ
読書感想文なんてどう書いたらいいかわからない。
まず、本を読むのが苦手。
そんな人に読んでほしい。
物語を読めば、本の選び方から、読み方、感想文の書き方まで、ひとつひとつ「読書感想文のコツ」を教えてくれます。

大人である私の感想
感想文の書き方ってコツがあるんだなと知るだけでも、おもしろい。
コツをつかんじゃえば、読書感想文なんか怖くない!!
『脚本家が教える読書感想文教室』

人気の読書感想文書き方講座を体験できる
習い事アプリ「ストアカ」の評価が☆5。最優秀講座賞を4年連続受賞。4500人以上の子どもが受講し、予約がとれない教室として知られる篠原明夫先生の読書感想文書き方講座のメソッドが1冊になりました。毎夏大人気の講座のメソッドを試してみてください。
【Amazon本紹介より】
●画像をクリックするとアマゾンへ
【著者】篠原明夫
【出版社】主婦の友社
小説ではありません
●あらすじ
対象は小学1~6年生(フリガナつき)。
中学生でも本、読書感想文が苦手な人にはおすすめ。
レッスン形式なので、何をどう学ぶかがわかり、しっかり頭に入ってきます。
イラストや図が多く、原稿用紙に書かれた見本作文による添削などで読みやすく、わかりやすくなっています。

大人である私の感想
参考書のようにイラストや図が多いので、本を読むのが苦手でも、読みやすい!
「自分の意見や気持ちを文章で書く」ことがカンタンになります。
『読書感想文が終わらない!』

感想文を書けば悩みもスッキリ?!
●画像をクリックするとアマゾンへ
【著者】額賀澪
【出版社】ポプラ社
●あらすじ
モヤモヤする気持ちを胸に抱える小学生たちが、夏休みの図書室で出会ったのは不思議な中学生フミちゃん!
彼女がおすすめする本を読むと……。
フミちゃんは読書感想文の神なのかも!?
物語を読むだけで、読書感想文を書くコツがわかる画期的な本です。
読書感想文からはじまる6人の特別な夏の物語。
●その他情報
巻末に、読書感想文の書き方メモ「フミちゃんの特別教室」あり

大人である私の感想
感想文を書くのって、今の自分の気持ちを文章にして外にはきだすことなんだなと思った。
友達
小学高学年生、中学生には「友達」ってすごく大事だけど、悩みのタネにもなる。
だからこそ、自分の言葉で読書感想文が書きやすいテーマです。
『むこう岸』

友情パワーで、生まれた環境を変えられるか?
●画像をクリックするとアマゾンへ
【著者】安田夏菜
【出版社】講談社
●あらすじ
有名進学校で落ちこぼれ公立中学に転校した、裕福な家庭で育った少年、和真。
父を事故で亡くし、母と妹と三人、生活保護を受けて暮らす少女、樹希。
まったく違う環境で育った二人は、お互いのことをまったく理解できなかったのだが。
互いことを知るにつれて、自分だけが現状の環境に苦しんでいるわけではないと、相手を思い合えるようになり……。
そして二人は自分たちの方法で、「貧しさゆえに機会を奪われる」不条理に立向かう。
どんなことだって、将来をあきらめる理由になんてならない!

大人である私の感想
最初は、正反対の環境で育ちながらも、あらがえない両親(家族)の”呪い”にしばられているふたりの心の痛みが読んでいて、ただただ辛かった。
でも、どうしようもできない状況に自分自身はあきらめているふたりが互いに、相手を助けてあげたいと思う気持ちをもち、さらには行動をおこす姿に「カッコいい」と思った。
人は、こんなにも誰かのために強くなれるのかと感動しました。
2021年度、広尾学園中学校の中学入試で出題された
『ハーベスト』

第一印象だけで友達を決めてない?
●画像をクリックするとアマゾンへ
【著者】花里真希
【出版社】講談社
●あらすじ
自分に自信がないおとなしい少年、中学1年生の朔弥。
思ったことをきちんと話せない、人に伝えられない、人と話すのが苦手な朔弥くんは、学校でも、家庭でも人との関りをなるべく避けていたのに。
ラクチンと思って入部した「園芸部」。
そこには、彫の深い顔立ちをしてちょっと怖い西森くんと、なぜかいつもうす汚れたユニコーンのぬいぐるみを抱えたアメリカからの帰国子女の先輩アズサしか部員はいなかった!
へんな部活に入っちゃったのかも……。
朔弥くん、強烈な仲間とともに「園芸部」で上手くやっていけるのか?

大人である私の感想
周囲の人たちのウワサや、偏見ってアテにならないな。
初めて会ったときからぜったいに仲良くなれない、苦手と感じた友達が大切な友達になるかもと思うとなんだかワクワクします。
2024年度、成城学園中学校の中学入試で出題された
『跳べ、暁!』

つらいのは自分だけじゃない!!
●画像をクリックするとアマゾンへ
【著者】藤岡陽子
【出版社】ポプラ社
●あらすじ
バスケにかける情熱とバスケを通じた友情がキラキラ光る青春物語と思いきや……。
中学生の子どもたちには、どうにもならない問題ってありますよね。
親の仕事の都合だったり、家族の金銭状態だったり、両親との相性不一致だったりと、悩んでも解決できないことって割とあります。
『跳べ、暁!』には、そんな悩みをもった女子中学生たちの物語。
父親と二人暮らし、中学2年の暁(あかつき)ちゃんを始め、苦しい立場にいる彼女たちは、仲間とバスケットボールをしているときだけは、悩みも忘れて熱中できるのです!

大人である私の感想
親に振り回される子どもたちが、辛い現実を受け止めながらも前を向き生きている姿に、大人としてはいたたまれない気持ちになった。
彼女たちが、お互いの悩みを分かち合い友情を深めて成長していく姿がキラキラしていて、何もできない大人としては「許された」気分にもなってしまった。
2021年度、聖ドミニコ学園中学校の中学入試で出題された
『天満つ星』

自分が友達のためにできることってなんだろう?
●画像をクリックするとアマゾンへ
【著者】中村汐里
【出版社】小学館
●あらすじ
希望していた難関私立中学校に入学した室本さくら。
新しい中学生活は、ワクワクすることでいっぱいのはずだったが、友人関係、入部した調理部の先輩との関係などなど、悩みもいっぱい。
そんななか、入部した調理部でお菓子コンテストに挑戦することに!
問題ひとつひとつに向き合い、クリアし、成長していくさくらの青春スイーツ小説。
●その他情報
前作『殻割る音』あり

大人である私の感想
周囲から煙たがれている先輩の隠された秘密には心が痛くなりました。
中学生にはどうにもならない現実だけど、少しでも先輩を助けたいと思うさくらちゃんの気持ちや行動に真の友情の姿をみました。
一方で、同級生の小学時代と中学時代の友達の間でオロオロするさくらちゃんの姿もリアルでした。
2025年度、長崎県の公立高校入試で出題された
『キャプテンマークと銭湯と』

友達になるのに必要なことってなんだろう?
●画像をクリックするとアマゾンへ
【著者】佐藤いつ子
【出版社】KADOKAWA
●あらすじ
キャプテンの座をとられてしまった中学生の周斗。
自分へのイライラをチームメイトに八つ当たりをしたことでチームから孤立してしまう。
そんな自分がいやになっていた周斗を助けてくれたのは……。
中学男子の成長・友情・青春物語。

大人である私の感想
友だちになれるのは、同じクラスメイトや同じ年れいの人、習い事や部活の仲間だけじゃない。
もしクラスやチームで孤立しても、ちがった場所に友だちがいるならさみしくない。
そして、友達をつくるには自分の殻を打ち破らなくちゃならないんだ!と教えてくれた。
2022年度、専修大学松戸中学ほか多数の中学入試で出題された
『友だち幻想』

友だちっていなくちゃいけないの?
●画像をクリックするとアマゾンへ
【著者】菅野仁
【出版社】筑摩書房(ちくまプリマー新書)
小説ではありません
●あらすじ
「友だち」について書いてある本といえば、この本というぐらいのベストセラー本!
「みんな仲良く」という重圧に苦しんでいるならぜひ読んでほしいです。
「みんな仲良く」のプレッシャーとは、”さようなら”する方法、人間関係を根本から見直す実用的な方法とは?!
人付き合いのルールを学び、複雑な人間関係の中で必要以上に傷つかず生きられるようになるために必読です。
「みんな仲良く」という幻想から逃れられましょう!

大人である私の感想
いくつになっても悩みのタネになる「友達」「人間関係」。
どうしてこんなにもうっとうしく、私を苦しめるんだ!という考え方から、なんでこう考えてしまうのかを考えるという、新しい見方で「友達」「人間関係」をとらえるのって新鮮だなと思った。
2022年度、和洋国府台女子中学校の中学入試で出題された
『悪口ってなんだろう』

学校生活の敵!?悪口について考えてみる
●画像をクリックするとアマゾンへ
【著者】和泉悠
【出版社】筑摩書房(ちくまプリマー新書)
小説ではありません
●あらすじ
生きていくなかで避けられないもの「悪口」
言ったことない、言われたことないなんて人いるんでしょうか?
でもそもそも「悪口」って悪いことなのか?どこから「悪口」になるのか?
「悪口」について真剣に向き合ってみたら、もう「悪口」が怖くなくなるかも!!
●その他情報
テレビ番組「カズレーザーと学ぶ。」で紹介された

大人である私の感想
「悪口」が怖いとずっと思っていたけれど、「悪口」について考えたことってなかったし、考えてみるなんて思いもしなかったのでタイトルから衝撃できした。
「悪口」って言葉のとらえ方も人それぞれなんだと思うと、「悪口」がちょっと怖くなくなるかもと思いました。
2024年度、甲陽学院中学校の中学入試で出題された
家族
小さなころから毎日ずっと一緒に過ごしている家族は、あなたの生活の基盤です。
選べないけれど大切な、あなただけの家族について考えてみると感想文が書きやすいです。
『奮闘するたすく』

大好きなおじいちゃんが変わっていく?
●画像をクリックするとアマゾンへ
【著者】まはら三桃
【出版社】講談社
●あらすじ
学校の先生の提案(という名の、ほぼ指示)で、たすくは友達の一平と一緒に、祖父が通うことになったデイサービス(通所介護施設)の体験レポートを書くことに。
最初は気が重かったたすくだけど、認知症が進んでいくおじいちゃんの現実に向き合いながら、子どもみたいに無邪気なお年寄りたちとのふれあいや、スタッフとのやり取りを通して、少しずついろんなことを感じていきます。
そして、たすくは気づくのです。
おじいちゃん自身も「自分が認知症になった」ことに戸惑い、苦しんでいる――そんな心の奥の気持ちに。
大切なおじいちゃんの変わりゆく気持ちや姿を理解していく貴重な夏休みが書かれた物語です。

大人である私の感想
自分がわからなくなるおじいちゃん……。
そんなおじいちゃんを心配する孫のたすく君の気もちだけじゃなく、おじいちゃんの不安を抱えた気持ちも丁寧に書かれていた。
お年寄りと実際に一緒に過ごしてみないとわからないことが、ぎゅっとつまっていた。
2018年度、栄光学園中学校の中学入試で出題された
『朔と新』

変わってしまった兄を家族はどう受け入れるのか?
●画像をクリックするとアマゾンへ
【著者】いとうみく
【出版社】講談社
●あらすじ
*朔(兄)
弟と乗った高速バスが事故にあい、失目してしまった
*新(弟)
高校1年生 兄の失目の原因は自分だと思っている
失目した朔を気遣い、ぎこちなさがのこる兄弟、家族。
そんななか、朔がブラインドマラソンに挑戦したい、新に伴走をお願いしたいと言い出した!
兄弟、家族とのすれ違い、思いもよらない人生の壁への葛藤をどう乗り越えていくのか?
絶望からの希望を書き出した感動物語

大人である私の感想
「もうダメかも」と思ったときに見えた今までとは違った家族の姿が、実は真実なのかも。
それは、表面だけの家族をぶっ壊し、新しく家族をつくるチャンスなのかもと思いました。
にしても、朔と新のお母さんは、なかなかのくせ者でした。
兄弟の女友達へのいやらしさや、息子への愛情の表現の仕方の描写が妙にリアルなのも読みごたえあります(笑)。
2021年度、ラサール中学、栄光学園中学、浦和明の星中学、淑徳与野中学の中学入試で出題された
『いいたいことがあります!』

親の考えがすべてじゃない!!
●画像をクリックするとアマゾンへ
【著者】魚住直子
【出版社】偕成社
●あらすじ
中学受験をひかえた小学6年生陽菜子
自分で決める大切さを知る成長物語
小学6年生の陽菜子にはよくわからないことがたくさんある。
陽菜子には、家の手伝いをさせるのに、いそがしいという兄は家事をしなくていいし、中学受験もしたいんだかどうかわからないし。
イライラが募る陽菜子はある日、運命の出会いをします!
●その他情報
陽菜子のお兄ちゃん目線で書かれた続編『考えたことなかった』があります。

大人である私の感想
だれもが感じたことのある、親と自分の考え方の違いが生み出す葛藤から、正しさはひとつじゃない。
大事なことに気づいた陽菜子ちゃん。
私にも、親や先生といった大人を”全能の神さま”のように思っていた子ども時代からの脱皮の時期がきた!
と思ったら、陽菜子ちゃんを参考にして上手く脱皮できるように(笑)。
2022年度、女子美術大学付属中学入試で出題された
『天の台所』

新しい家族をつくろう!
●画像をクリックするとアマゾンへ
【著者】落合由佳
【出版社】講談社
●あらすじ
長編物語
祖母が亡くなってしまい、現在は、父と弟と妹と4人暮らす小学6年生の天くん
「台所は、家の心臓なんだよ」
そんな、おばあちゃんの言葉から物語は始まります。
祖母が亡くなり、だれも料理をすることがなくなってしまった天くんのお家。荒れ放題の、うちのなかやおばあちゃんの台所。
天くんは、お隣に住む、ちょっと怖い「がみババ」から、厳しく料理を習い始めます。
生きるために、家族再生のため、おばあちゃんの台所を守るため料理をマスターしていく天くんの成長物語。
●その他情報
続編『要の台所』あり。
➡「異文化」のコーナーで紹介しています。

大人である私の感想
料理とは、食べてくれる人を想い、台所に立ち、道具を駆使し、食材を選び、メニューを考え、洗い物といった後片付けもする、そんな一連の流れが毎日毎日繰り返されて、おいしい料理が食べられるのに気づく天くん。
そしてその料理が、家族を元気づけ、明るくし、気持ちをひとつに繋いでくれる。
天くんを通して、食事と家族の大切さやありがたさをかみしめよう!
2024年度、普連土学園中学校の入試で出題された
『街に躍ねる』

家族だからこそ難しい
●画像をクリックするとアマゾンへ
【著者】川上佐都
【出版社】ポプラ社
●あらすじ
兄弟、姉妹はいますか?
そして兄弟、姉妹は好きですか?
もし大好きな兄弟、姉妹が世間から「普通じゃない」といわれていたら……。
小学5年生の晶と高校生の達、仲良し兄弟物語です。

大人である私の感想
大好きな家族が、ちょっとほかの人とは違うと思ったことあります。
大好きなんだけど、友達には話したくない家族のこと。
自分のなかでモヤモヤする気持ちってイヤなんだけど、どうしていいかわからない。
なにがどうイヤなのかもわからない。
家族って、自分の大切なものだからこそ難しい。
2024年度、大妻多摩中学校の中学入試で出題された
生き方
生きていれば、楽しいことばっかりじゃない、壁にぶつかったり、どうにもならない現実にうちのめされる日もある。
でも、明日はやってくるし、生きなければならない。
そんなときに、勇気をもらえる本を読んで感想を書いてみよう。
『カラフル』

今まで、できていたことができなくなったら?
●画像をクリックするとアマゾンへ
【著者】阿部暁子
【出版社】集英社
●あらすじ
やる気なしの男子、荒谷伊澄が高校入学式の朝に駅で出会った少女は車イスに乗っていた。
車いすの少女、渡辺六花はなんと同じ高校の新入生!
伊澄は、気の強い六花に最初は圧倒されていたのだが、じょじょに本当の六花の姿を知っていく……。
高校生の成長青春そして恋の物語!

大人である私の感想
車いすの生活ではどうにもならないこともあるという、過酷な現実。
そして、強いとおもっていた六花が心のうちに秘めている不安や怖さ、絶望はどれほどなのかと思うと泣けてしまった。
そしてそれを受け止めてあげようとする伊澄が変わっていく姿には胸キュンでした。
自分が大きな壁にぶつかったとき、大切な人が大きな壁にぶつかったとき、自分はどうなるのかと考えてしまいました。
2025年度、森村学園中学校の中学入試で出題された
『透明なルール』

生きるのが窮屈なのって、どうしてなんだろう?
●画像をクリックするとアマゾンへ
【著者】佐藤いつ子
【出版社】KADOKAWA
児童書
●あらすじ
しっかりもので成績優秀な中学生・優希は、家でも学校でも”言いたいこと”が言えないし、本当の自分を隠している。
なぜかといえば、「周りからどう思われるか」が怖いから。
生きづらさを感じる優希が、自分を縛っているものに気づく!
いったいそれは何だったのか?
そして、それに打ち勝つことはできるのか?

大人である私の感想
「いい子ちゃん」でいるのもたいへん。
勉強、運動ができるとみんなに知られるのがイヤ、先生にほめられるのもイヤ
とにかく目だたないで、みんなと同じでいたいって気持ちと、それに縛られるのが辛いっていう両方の気もちのバランスが難しいなと思った。
2025年度、早稲田実業学校中等部の中学入試で出題された
『あの空の色がほしい』

自分の好きなもので、生きていけるのか?
●画像をクリックするとアマゾンへ
【著者】蟹江杏
【出版社】河出書房新社
●あらすじ
近所にステキな名前の美術教室をみつけた小学4年生の少女マコちゃん。
絵を描くことが大好きな少女はその教室に通うことにするのだが……。
先生は見た目”怪しげな”、教え方”普通じゃない”おっさんだった!!
クラスメイトと自分との考え方や行動にギャップを感じながらも、自分の好きなこと、絵を描くことで自分を表現できることを知る少女の成長物語。

大人である私の感想
好きなことを貫くこと、自分らしく生きるのってこんなにも難しいんだ。
それにはイヤなこと、辛いこと、悲しいことも経験しなくちゃなんだ……。
それでも、好きなことをすればするほど、もっともっと好きになる楽しさや、興奮、ワクワクがたくさん味わえるんだと思うのです。
自分の人生をどう生きるのか?考えて実行できるのは自分しかいないんだなと心に響きます。
2025年度、久留米大付属中学校の中学入試で出題された
『正しいパンツのたたみ方――新しい家庭科勉強法』

ひとりで生活できる?
●画像をクリックするとアマゾンへ
【著者】南野忠晴
【出版社】岩波書店(岩波ジュニア)
小説ではありません
●あらすじ
作者の南野さんは、大阪府立高校で初の男性家庭科教員のひとりになった人です。
パンツのたたみ方がキッカケで夫婦喧嘩になったら??
掃除や洗濯、料理、片付けといった家事、お金の使い方を学ぶのが家庭科ではない!
自立のために自分の暮らしを自分で整える力はもちろん、社会の中でどう生きていくかを教えてくれます。

大人である私の感想
10代の頃にこの本を読んでいれば……。
自分の人生を生きられるのは自分しかいないんだから、自分が幸せに生きるには、役立ついろいろな知識を得ておくのが大切なんだなと思った。
2024年度、立正大学中学校の中学入試で出題された
『“正しい”を疑え!』

それって正しいの?
●画像をクリックするとアマゾンへ
【著者】真山仁
【出版社】岩波書店(岩波ジュニア新書)
小説ではありません
●あらすじ
「自分はぜったいに正しい」
「自分は間違っているのかも」
SNSをみるたびに不安と不信に陥っていませんか?
何を信じ、何をよりどころにすればよいのか?
自分を信じて、自分らしく生きるためのヒントを教えてほしいと思いませんか?
交渉の考え方や、推理力を高める方法など実際の生活に役立つことが書かれています。

大人である私の感想
いろんな情報があって、いろんなウワサがあって、いろんなアドバイスがあるけれど、結局何が正しいんだろうって思うことが多い。
「心のよりどころ」、そしてそれを常にアップデートできる余裕をもちたいなと思った。
2024年度、青山学院中等部、桜美林中学校、鷗友学園女子中学校など多数の中学入試で出題された
戦争
夏といえば、終戦記念日や原爆投下日など戦争について考えることが多いので、読書感想文のテーマとしておすすめです。
『昔はおれと同い年だった田中さんとの友情』

戦争のリアルを知ろう
●画像をクリックするとアマゾンへ
【著者】椰月美智子
【出版社】双葉社
●あらすじ
小学6年生の少年3人と、85歳の田中さんとの交流を描いたさわやかな友情物語といいたいのですが……。
仲をふかめていくうちに知る田中さんの秘密が明らかになっていきます。
戦争を体験した田中さんが、11歳の子どもたちに伝えたいこととは?

大人である私の感想
戦争は物語やゲームの中のものではないのです。
穏やかな田中さんからは想像できない……。田中さんが受けた「戦争体験」には心が痛くなる。
戦争によって傷つく人たちが大勢いるのをわかっていて、どうして人は戦争をするのだろうか?
謎すぎる。
2024年度、京華中学校の中学入試で出題された
☟文庫本
☟児童用(単行本)
『ある晴れた夏の朝』

原爆投下について考えたことある?
●画像をクリックするとアマゾンへ
【著者】小手鞠るい
【出版社】偕成社
●あらすじ
時代は1980年代、アメリカの8人の高校生が、広島・長崎に落とされた原子爆弾の是非をディベート(討論)をする物語。
参加者は、日系アメリカ人のメイ(主人公)をはじめ、アイルランド系、中国系、ユダヤ系、アフリカ系と、人種や彼らのバックグラウンドが違う面々。
だからこそいろんな意見が飛び交います。
原爆の話をきっかけに、真珠湾攻撃、南京大虐殺など戦時中に起こったことについても取り上げられ、さらに、人種の問題にも発展していきます。

大人である私の感想
原爆をつくって日本に落としたアメリカでは、原爆についてどんなふうに考えられているのか考えたことありますか?
原爆投下に賛成している人だって、戦争はしたくない、平和を願う気持ちは、日本人もアメリカ人も、世界中の人が望んでいるのだと思いました。
それにしても、ひとつの問題から、こんなにもたくさんの問題があふれ出てくるのかとアメリカの若者たちの問題意識の高さにビックリでした。
2020年度、麗澤中学校の中学入試で出題された
☟文庫本で読む
☟児童書で読む
『アンネ・フランク』

アンネ・フランクを知ってる?
●画像をクリックするとアマゾンへ
【著者】岡田好惠
【絵】佐竹美保
【出版社】講談社
小説ではありません
●あらすじ
アンネ・フランクの伝記
戦争中ユダヤ人のアンネ・フランクは、隠れ家で暮らしていた!
彼女はどうしてそんな暮らしをしなくちゃいけなかったのか?
13歳の少女が2年間も隠れ家でじっと暮らすなんて、信じられる??
戦争の悲劇は、戦地でおこっているだけじゃないのです。

大人である私の感想
戦争という自分一人ではどうにもならない過酷な状況のなかでも、生きることを諦めなかったアアンネ。
しかもそんな日々でさえも、毎日を楽しくすごそうとするアンネ。
私は、アンネと友だちになりたいといつも思うのです。
2024年度、アンネ・フランクについての問題が郁文館中学校の中学入試で出題された
『杉原千畝 命のビザ』

こんなスゴイ日本人がいたって知ってる?
●画像をクリックするとアマゾンへ
【著者】石崎洋司
【絵】山下和美
【出版社】講談社
小説ではありません
●あらすじ
第2次世界大戦中に、リトアニアの日本領事館の領事代理になった外交官、杉原千畝(すぎはらちうね)の伝記。
ナチスによる迫害に苦しむユダヤ人を間近でみていた杉原千畝のとった行動とは?
きびしい戦争のなかで、勇気ある信念と決断力をあなたはもてるか?!

大人である私の感想
恥ずかしながら、大人になるまで知らなかった杉原千畝さん。
フランク・アンネの本を合わせて読むと、杉原千畝さんの行動がどれほど危険で、勇気あるものだとわかり、ただただ「すごいな」と尊敬してしました。
杉原さんほどの大きな決断でなくとも、自分の決断には責任をもてる人でありたいと思います。
2024年度、開成中学校の中学入試(社会)で「杉原千畝」についての問題が出題された
多様性 ジェンダー・マイノリティ
「男とか女とか関係ない!」「生き方はその人の自由」とは言われても、なかなか生きにくい世のなかだよなと思っている人におすすめのテーマです。
『わたしの気になるあの子』

男とか女とか関係あるの?
●画像をクリックするとアマゾンへ
【著者】朝比奈蓉子
【出版社】ポプラ社
●あらすじ
祖父の男と女の考えにウンザリ、小6年の瑠美奈ちゃん
おじいちゃんの男と女への考え方にウンザリしている瑠美奈ちゃん。
そんなときクラスの転校生、詩音ちゃんが突然坊主頭で登校してきた!
からかう男子、引き気味の女子、ただでさえ独りぼっちだった詩音は、さらにクラスから孤立してしまいます。
詩音ちゃんはなぜ坊主頭になったのか?
詩音ちゃんの気持ちを知った瑠美奈ちゃんは驚きの行動にでます。

大人である私の感想
いろんな考え方の人がいる社会の中で自分らしく生きるのは難しい。
けれど、人と人と助けあいながら、自分を知ってもらい、相手を知ってお互いを理解しながら生きていくのって、自分にも友達にも大切なんだなと思いました。
2022年度、洗⾜学園中学校、浦和明の星中学校、桐朋女子中学校、成城中学校の中学入試で出題された
『ぼくのまつり縫い: 手芸男子は好きっていえない』

男だからスポーツが好きと思っていない?
●画像をクリックするとアマゾンへ
【著者】 神戸遥真
【出版社】偕成社
●あらすじ
手芸や料理は女の子の趣味、スポーツやモノづくり作業(DIY)は男の趣味として思っていませんか?
そんなことはまったくありません。
だって一流の料理人の多くは男性ですしね。(それはそれでまた問題があるようですが(笑))
サッカー部だった優人はケガをきっかけに、あれよあれよと被服部のお手伝いをすることになります。
でもそれはみんなに隠しておきたいことなんだけど……。。
被服部の活動はむちゃくちゃ楽しい!!
ゆらゆら揺れる優人はどうするのか?
●その他情報
シリーズ化している
『ぼくのまつり縫い 手芸男子とカワイイ後輩』
『ぼくのまつり縫い 手芸男子と贈る花』

大人である私の感想
みんなと同じが安心な中学生にとって、男子で「手芸が好き」って言うのはなかなかヘビーな問題だろうと読んでいて心を痛めたのだが。
でも、彼を見守ってくれる仲間たちの優しさには逆に驚いた!
今どきは大人が思うよりも、それぞれの好きなことが「当たり前」に認められるようになっているのかもしれない。
2021年度、茨城県の公立高校入試で出題された
『はずれ者が進化をつくる –生き物をめぐる個性の秘密』

生き物たちから教わる!「生きのびるコツ」とは?
●画像をクリックするとアマゾンへ
【著者】稲垣栄洋
【出版社】ちくま書房(ちくまプリマー)
小説ではありません
●あらすじ
生き物ってみんなちがう見た目だし、ちがく生き方をしています。
それには理由、生存戦略がある!?
「個性」「ふつう」「区別」「多様性」「らしさ」とか言われるけれど、それって何なんだろうか?
そして生きるのには「勝つ」ための「強さ」が必要なのか?
生きるのに「大切なもの」は何か?
そもそも「生きる」とは何か?
生き残るのはだれなのか!!
●その他情報
9のテーマごとの時間割形式で、授業をうけるように読めます。
イラストや図なども豊富にあり、小学高学年でも読みやすいです。

大人である私の感想
がんばって生きているのって、なんのためなんだろうか?
私たちはどうして生まれてきて、この地球で暮らしているのか?
そこに意味はあるのか?
大人になるまで考えたこともなかった疑問がわいてきました。
2021年度、多数の中学校の入試で出題された
異文化
世界中の国の人たちとコミュニケーションをとって生きていくのが当たり前になってきたからこそ読んでおきたい。
海外の人たちとの交流も増えてくると、思いがけない問題にぶつかることがあります。
そんなときどうしたらいいのかを考えてみるキッカケになります。
外国人と接したことのない人でも、読んで思ったことを感想文に書いてみてください。
『要の台所』

文化や習慣が違うと友だちになれないのかな?
●画像をクリックするとアマゾンへ
【著者】落合由佳
【出版社】講談社
●あらすじ
要は引っ込み思案の中学1年生の女の子。
自分に自信がない……、クラスでうすい存在の自分がイヤだ!
でもそんな自分でもだれかの支えになれるかな?と思う要ちゃん。
そんな彼女が友達になりたい!と思ったサリタちゃんはネパールから来たお隣さん、ひとつ年上の女の子。
サリタと友達になるために、近所の「がみババ」に料理を教わることに。
料理で文化の違うサリタと仲良くなれるか!?

大人である私の感想
要ちゃんとサリタちゃん、なかなかスムーズに心を通わせることができないのもリアルでした。
でも、失敗してもあきらめない要ちゃんから、文化のちがう人たちと仲良くなるために必要なことを教えてもらいました。
相手を知ることも、自分を知ってもらうことも友達になる基本がやっぱり必要なんだと思います。
2025年度、田園調布学園中学校の中学出題された
『リマ・トゥジュ・リマ・トゥジュ・トゥジュ』

自分の考えが世界共通って思っていない?
●画像をクリックするとアマゾンへ
【著者】こまつあやこ
【出版社】講談社
●あらすじ
主人公は、マレーシアからの帰国子女の沙弥ちゃん
沙弥ちゃんは、マレーシアに住んでいたのは2年ほどで日本人感覚を知っているのですが、どうも日本の中学校生活に違和感を感じてしまいます。
早く、日本の学校生活に馴染もうとする沙弥ちゃんですが、なぜか、図書委員の先輩に誘われて短歌を詠み始めることに……。
え!短歌?
と思っていたら、そこから恋心が関わってきたり、宗教がかかわっていきたりと物語は大きく展開していきます。
ちなみにタイトルの『リマ・トゥジュ・リマ・トゥジュ・トゥジュ 』は、マレーシア語で5・7・5・7・7の意味です。

大人である私の感想
友達、家族、異文化、短歌、恋、あらゆる悩みや話題が盛りだくさんに詰まっていました。
自分の価値観や考え方が、すべてではない。
まわりをみて、相手の気持ちを考えられるような人でいたいなと思います。
2019年度、多数の中学校入試で出題され話題になった
『となりのアブダラくん』

言葉も文化も宗教も違う子がクラスメイトになったら?
●画像をクリックするとアマゾンへ
【著者】黒川裕子
【出版社】講談社
●あらすじ
ある日、あなたのクラスにパキスタンからの日本語を話せないイスラム教の転校生がやってくる。
しかもあなたは、転校生のお世話係になってしまったら?
宗教が違うし、文化も、見た目もちがうし、うまく言葉も通じないアブダラくんがクラスにやってきます。
みんなと違うだらけのクラスメイトたちと、転校生のアブダラくん。
お世話係になった小学6年生の男子、晴夜くんは、アブダラくんを助けてあげられるのでしょうか?
そして、実は晴夜くんは友達にも話していない秘密があるのです。
その秘密を友達に告白できるのか?!

大人である私の感想
ビックリしちゃうようなアブダラくんの行動も、アブダラくんには普通のこと。
日本の中で当たり前や普通が世界では普通じゃないことがあるって驚きだけど、それを知るたびに「ああ、世界って広いな、おもしろいな」と思うのです。
2022年度、聖学院中学校の中学入試で出題された
『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』

英国の中学生の暮らしは?
●画像をクリックするとアマゾンへ
【著者】ブレイディみかこ
【出版社】新潮社
小説ではありません
●あらすじ
イギリスに住むブレイディさん家族のリアルな日常が書かれたエッセイ本です。
息子さん13歳、中学に入学するところからエッセイは始まります。
自分がマイノリティ(少数派)と常に感じている日本人の母みかこさんと、日本人の母をもち東洋人顔の息子さんのイギリスでの生活とは?
思春期の息子さんの友達との関係や、勉強のこと、親子関係の悩みとは?
そんな息子さんに母親のみかこさんが教えることとは?
母と息子が一緒に考え、悩むこととは?
多様な人種が暮らすのが当たり前のようなイギリスでも、アジア人が暮らすのはたいへん……。
母親のみかこさんは息子さんに、自分のこれまでの体験を語り、社会の不条理を教え、そして息子さんと一緒に社会の問題について考えるのです。
●その他情報
続編『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー 2』あり

大人である私の感想
いろんな人たちが住む世界で、自分らしく生きていくのに、知っておくべきことがたくさんあった。自分が社会の中でマイノリティ(少数派)になったときこそ、自分らしさが必要になるんだと思う。
それにしても、こんなカッコいいお母さん(ブレイディみかこさん)うらやましいです。
そして、母親の姿を見ながら、思春期の悩み、疑問に思ったこと、社会のひずみを自分できちんと受け止めて考えていく、みかこさんの息子さんもカッコいいです。
2021年度、芝浦工業大学付属中学校の中学入試で出題された
環境問題を考える
環境問題は難しいけれど、自分の身の回りから考えやすいテーマです。
本を読んで、自分ができるだろう環境問題の取り組みを感想文に書いてみるのがおすすめです。
『サステナブルビーチ』

海の豊かさを守ろるために、自分のできることってなんだろう?
●画像をクリックするとアマゾンへ
【著者】小手鞠るい
【出版社】さえら書房
●あらすじ
日本人の父とアメリカ人の母を両親にもつ小学6年生の男の子七海(ななみ)くん。
みんなとちょっと違う外見で、毎日が居心地が悪い……。
そんな七海くんは夏休み、お母さんとハワイへ出かけ、日本で感じていた違和感(顔が外国人風)からの解放感を味わいます。
そして、七海くんは、同じ年の女の子が、環境問題に自分のできることから取り組んでいる姿に衝撃を受け、この問題に対して自分なりに行動をおこそうと考えるのですが。
七海くんにできることってなんだろう?

大人である私の感想
世界中をつなげている海だからこそ、どこの国でも、海の環境問題についてアクションを起こしていかなくちゃいけなし、世界中が協力して取り組まなくてはならないことを教えてくれました。
ぜったいに、未来にも美しい海をつないでいかなくてはいけないな。
2024年度、東海大学付属高輪台高等学校中等部の中学入試で出題された
2023年度、明治学院大学中学校の中学入試で出題された
『生きるぼくら』

「米作り」ってたいへんなんだよ
●画像をクリックするとアマゾンへ
【著者】原田マハ
【出版社】徳間書店
●あらすじ
麻生人生、24歳。現在、ひきこもり生活中。
そんな彼のもとから、たった一人の家族──お母さんがまさかの家出!?
「え、これからどうやって生きてけばいいの……?」
行き場をなくした人生は、しぶしぶ別れた父の実家へ向かうことに。
でも、久しぶりに会ったおばあちゃんは認知症になっていて、人生のことを忘れていた。
しかもなぜか、見知らぬ女の子と一緒に暮らしてるってどういうこと!?
次々と巻き起こる”人生の転機”に、逃げ続けていた彼が少しずつ向き合っていく。
「人と関わるのが苦手」だった青年が、米作りを通して“自分らしく生きる”意味を少しずつ見つけていく成長物語。

大人である私の感想
「米づくり」に挑む人生くんの姿は「令和の米不足」問題を考えるキッカケにもなります。
いじめや引きこもり、農業の担い手不足、認知症、孤独、貧困…。
この物語には、いまの社会が抱える“リアルな問題”が詰まっていました。
でも、ただ重たいだけじゃない。
悩みながらも、不器用ながらも、前に前に進もうとする登場人物の生き方は、前向きになれる元気を与えてくれました。
2024年度、東京都市大学等々力中学校の中学入試で出題された
『捨てないパン屋の挑戦 しあわせのレシピ』

フードロス、環境問題から、自分の生き方や働き方を考える
●画像をクリックするとアマゾンへ
【著者】井出留美 (著)
【出版社】あかね書房
小説ではありません
●あらすじ
「捨てないパン屋」として有名な田村陽至さんの生き方を探る!
どうしてパン屋さんになったのか?
おいしいパンを作るためにしたこと、していること、そしてこれからしていくこととは??
パンつくりと、なによりも「自分」を大切にする田村さん流の生き方を学べます。
そしてそれは地球の環境にも繋がっていくのですが……。
どうつながるのでしょうか?

大人である私の感想
田村さんって何よりも自分の幸せを考えているんだけど、それが自分勝手になってないところがスゴイ!
パン屋さんという仕事はもちろん、田村さんの自分の人生を大切に考えていることにカッコいいなと思った。
自分が幸せになるために人間って生きているんだと教えてくれる本だった。
2022年 第68回青少年読書感想文コンクール<小学校高学年の部>課題図書
『2050年の地球を予測する ――科学でわかる環境の未来』

未来の自然はどうなっていくのかな?
●画像をクリックするとアマゾンへ
【著者】伊勢武史
【出版社】筑摩書房(ちくまプリマー新書)
小説ではありません
●あらすじ
毎年の異常気象って地球がヘンなの?
感情論、短絡的に結論を求めるのではなく落ち着いて環境問題を根本から考えると……。
さらには人間ならではの自然に及ぼす行動とは?
自然を守るために人間が選択する道をはあるのか?

大人である私の感想
世界規模での社会問題って難しい。
想像できないから、現実的問題としてとらえにくいし、解決方法がみつけにくいからだ。
そして、人間が快適に生きよう、社会を発展させようとすればするほど、自然環境が壊されていく事実は避けられないジレンマ。
2050年、遠いようで近い未来だなと思った。
2023年度、浦和明の星女子中学校の中学入試で出題された
2023年度、群馬県、宮城県、大分県、佐賀県の公立高校の入試で出題された
テーマ別 読書感想文が書きやすい本リスト
読書感想文が書きやすい本をテーマ別に紹介しています。
気になるテーマから、読んでみたいなと思う本をみつけてください。

あなたの好みの本を選んで読んでみてね。
感想文の書き方
友達
家族
生き方
戦争
☟文庫本
☟児童用(単行本)
☟文庫本で読む
☟児童書で読む


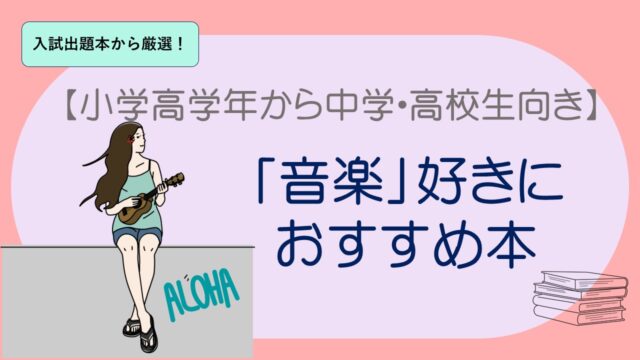
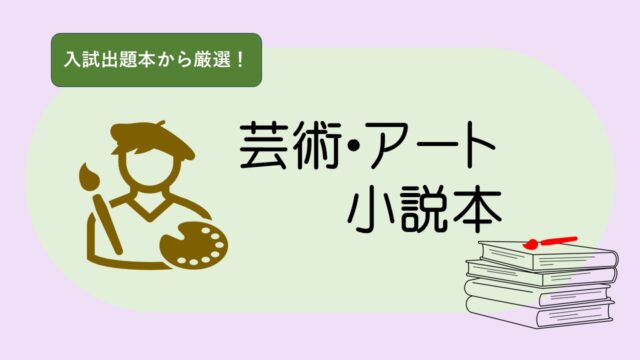
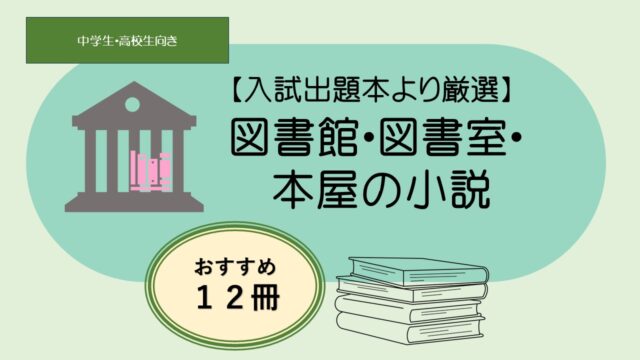

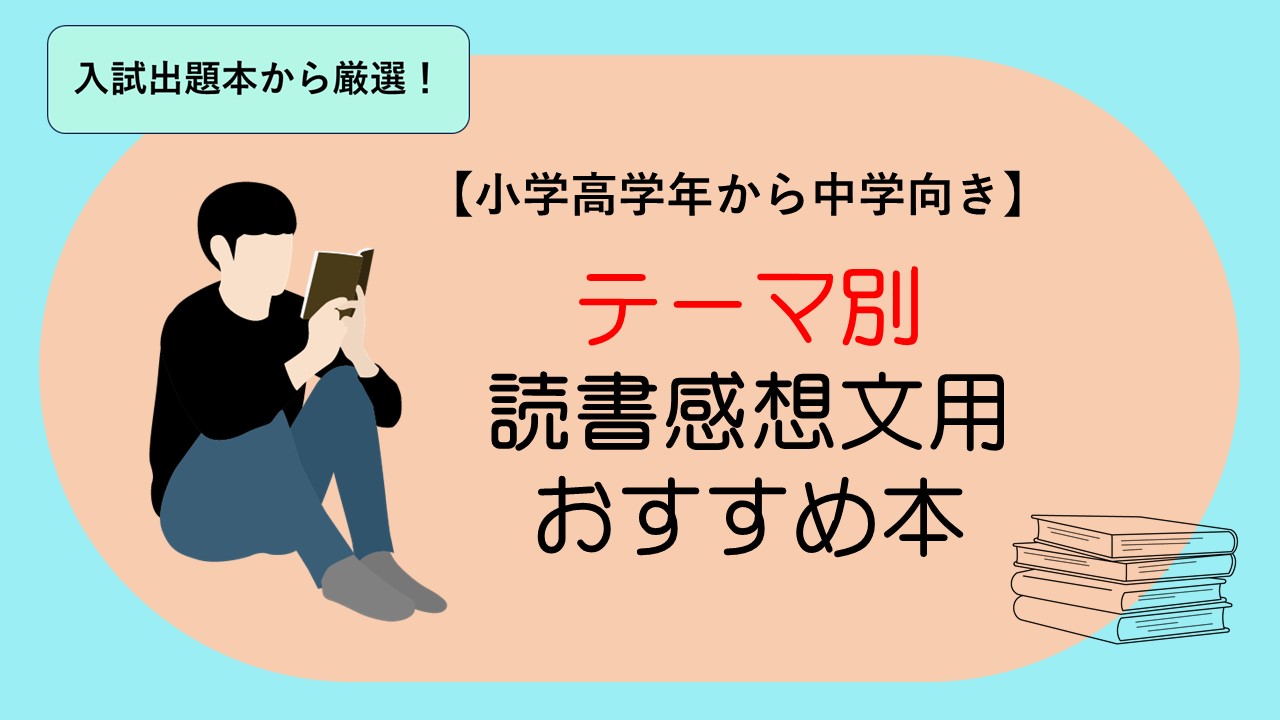



































コメント